
妊娠した喜びを感じたのも束の間、つわりや体調の変化に振り回されるママ。なかには、定期健診を受診して「切迫流産」という診断を受け、頭が真っ白になってしまった経験をした人も少なくありません。
あまりの衝撃に涙を浮かべる方も多くいます。しかし、切迫流産=赤ちゃんが亡くなったという訳ではありません。赤ちゃんは、まだママのお腹のなかで懸命に生きようとしています。
今回は、切迫流産について詳しく解説します。切迫流産の症状や原因、対処法と合わせて自宅療養を指示された際の過ごし方についても紹介します。切迫流産について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
切迫流産とは
切迫流産とは、妊娠22週未満の妊婦が流産を起こしかけている状態を指します。胎児は生きており、流産とは異なるので注意してください。
そのため、切迫流産と診断されてもその後の妊娠の経過に問題がなく出産に至るケースも多々あります。妊娠中はホルモンの変化によって精神的に不安定になりやすい状態です。切迫流産と診断されたからといって、悲観的にならず医師の指示に従って過ごすようにしましょう。
切迫流産の原因
切迫流産の原因は大きく2種類に分けられます。
妊娠12週未満で起こる切迫流産の原因
妊娠12週未満は妊娠全期のなかでもっとも流産を起こしやすい時期です。この場合、原因の多くは胎児の染色体異常等であると考えられ、対処することはできません。
対処法が無い為、安静にして様子を見るよう指示されることが多いでしょう。
妊娠12週以上で起こる切迫流産
妊娠12週以上で起こる切迫流産の場合、以下の原因が可能性として考えられます。
- 染色体異常
- 絨毛膜下出血
- 子宮の収縮
- 感染症など
状態によって、入院や自宅安静、子宮収縮を抑える薬を処方されることもあります。
切迫流産の症状
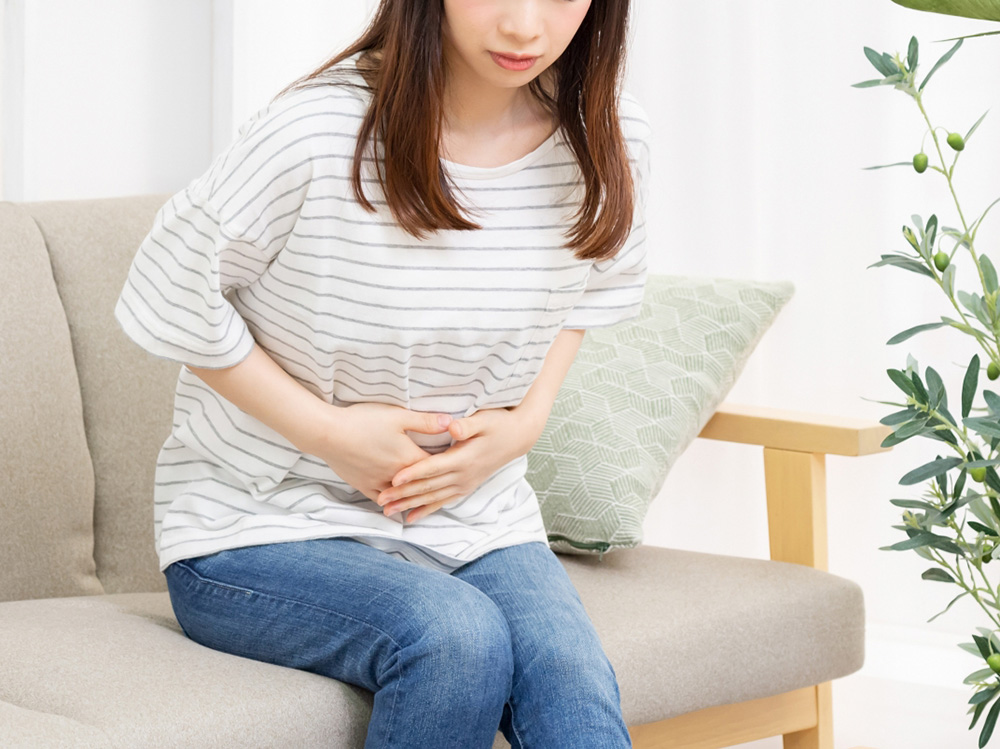
切迫流産の際には以下のような症状が見られることがあります。
- 下腹部の痛み
- 出血
- おなかの張り
上記の症状が見られる事があるものの、無症状のまま定期健診を受けた際に切迫流産であると診断されるケースも決して少なくありません。
切迫流産になると赤ちゃんに障害が残る?
切迫流産の診断を受けた際、お腹の赤ちゃんの事を心配に思うママが多くいます。妊娠の経過が悪いことで何らかの障害が残るのではないかと不安に思う人もいるでしょう。
切迫流産の場合、赤ちゃんは変わらず元気にいるケースも少なくありません。もちろん、先天的な遺伝子異常を持っているということが原因で切迫流産になりやすいという可能性はあるでしょう。しかし、健康で正常な遺伝子を持った胎児が切迫流産をきっかけに障害を持つという根拠はありません。
切迫流産の治療方法
切迫流産の治療方法は、状態によって変わりますが、大まかに妊娠12週未満と妊娠12週以降によって変わります。妊娠12週未満の場合、安静や様子見といった対処を指示されることが多いでしょう。生後12週未満の切迫流産では遺伝子異常が原因となるケースが多く、現代の医療では手の施しようがありません。
遺伝子異常によって起こる流産は、ママが仕事をしてようがスポーツをしてようが影響することはないと言われています。しかし、できる限り負担を減らすために自宅安静などを指示されることがあります。
妊娠12週以上で起こる流産では、現状を診察したうえで対処療法が選択されます。自宅安静や入院措置、お腹の張りを抑える薬の投与などから、医師が必要な処置を選択するケースが多いです。
切迫流産の診断を受けた時の自宅安静とは

切迫流産の場合、なるべく安静にして過ごし、現状以上に流産を進行させないために自宅安静の指示を受けることが多いです。特に、妊娠12週未満の場合は自宅安静にて様子を見るケースが非常に多いでしょう。
自宅安静の期間は2週間から1ヶ月以上など状態によって異なり、長期間に渡るケースもあります。
自宅安静ではどう過ごす?
自宅安静の指示を受けた場合、基本的に外出は控えましょう。自宅にてベッドで横になって過ごすのが望ましいです。できる限り家事なども控え、パートナーや同居家族が協力して対応できるよう話合う必要があります。重い物を持つ、動き回る、階段の上り下りをする、などの行動は腹圧がかかりやすいので控えてください。自宅安静中は、特に転倒などに注意し慎重に行動しましょう。
どうしても安静にするのが難しい場合は?
上の子どもがいる場合など、どうしても安静にするのが難しい人もいるでしょう。一時保育や親族の助けを受けて、可能な限り安静に過ごしてください。ベビーシッターや家事代行、ネットスーパーなどを上手に活用しましょう。
本当に一歩も動いてはいけない状態なのであれば、医師は入院措置を選択します。自宅安静の場合、様子見の意味合いも兼ねているので最低限の上の子のお世話や家事をしている人も少なくはないでしょう。
この時期の流産は、現代医学でも止められるものではありません。赤ちゃん自身の要因が非常に大きいと言えます。それでも、赤ちゃんに万が一のことがあった時に「あの時安静に過ごしていればもしかしたら…」と後悔してしまう事のないよう、周囲の協力を得て過ごす事を心掛けてください。
自宅安静の場合は仕事を休める?
仕事については医師に相談しましょう。基本的には休職としますが、いつからいつまで休職すべきなのかなど、指示を仰ぎ速やかに診断書を作成してもらうのが望ましいです。
会社に診断書を提出して、休業してください。会社には医師の指示にしたがって妊婦の健康管理を行う義務があるため、遠慮する必要はありません。母子手帳に添付されている「母性健康管理指導事項連絡カード」を医師に記載してもらい、職場に提出するのもよいでしょう。母性健康管理指導事項連絡カードは正式な証明書類として機能するため、休養後の勤務時間、時間外労働の制限、通勤時間の変更などを、医師から職場に指示してもらえます。
切迫流産で自宅安静し休職する場合に使える保障制度
切迫流産の場合、自宅安静による休職であっても条件が揃えば傷病手当金制度を利用して給付金が受けられる可能性があります。
以下の条件を満たしている場合、傷病手当金を受け取れる可能性が高いため問い合わせてみるとよいでしょう。
- 連続して4日以上の休業を医師から指示されている場合
- 健康保険に加入してから1年以上が経過している場合
- 休業中に有給休暇などを使わず給与の支払いがない場合
すべての要件を満たしている場合は、自宅安静による休養でも傷病手当金が受け取れる可能性があります。
切迫流産以外にも!流産の種類
切迫流産以外にも、流産にはさまざまな種類があります。自分自身に何が起こっているのか理解できるよう、流産の種類について知っておくとよいでしょう。
自然流産
胎児が人工的な処置もしくは感染症などの外部要因以外の原因で、子宮内にて亡くなった状態を指します。多くの流産が自然流産に該当します。
人工流産
人工的に生きている胎児を排出させ妊娠を終了させることです。人工妊娠中絶と同義の言葉です。
化学流産
妊娠反応は陽性なのに超音波検査で胎嚢が確認できる前に流産してしまった状態です。
稽留流産
腹痛、出血などの自覚症状がなく子宮内で胎児が死亡し留まっている状態です。妊娠7~9週に起こるケースが多く、原因の多くは染色体異常と考えられます。
進行流産
子宮内で胎児が亡くなっており、徐々に体外に排出されるよう進行し続けている状態です。その後、不全流産もしくは完全流産に移行します。
不全流産
子宮内で亡くなった胎児や組織が排出され、尚且つ一部が子宮内に残ることで出血、腹痛などを引き起こしている状態です。
完全流産
子宮内で胎児が亡くなり、胎児や組織がすでに排出されている状態です。
感染流産
子宮内に細菌、ウイルスなどが感染したことが原因で胎児が亡くなっている状態です。
まとめ
切迫流産の診断を受けるとどうしても不安や焦りを感じてしまうでしょう。しかし、まだ胎内で赤ちゃんは懸命に生きています。まずは落ち着いて、その時にできる最善の対応ができるよう行動してください。
コラム一覧に戻る




 Web予約
Web予約 011-885-1100
011-885-1100